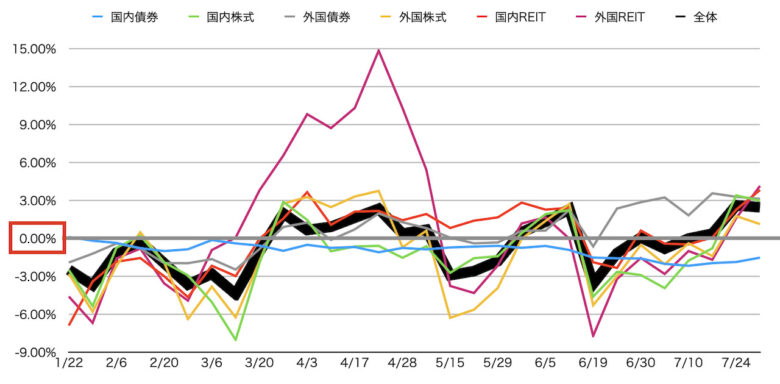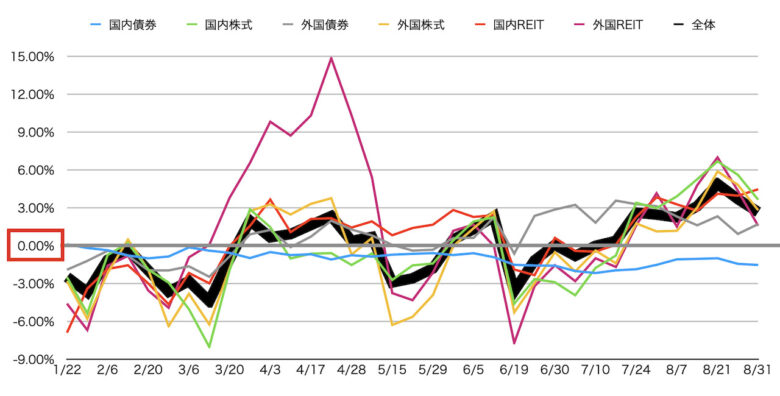個人の年金である、個人型確定拠出年金(iDeCo)は、運用にかかる手数料がかかります。TwitterやYouTubeを見ていると、
「iDeCoの手数料は高すぎる!ボッタクリだ!」
という内容のものが散見されますが、手数料がボッタクリなのかどうかは、所得控除額と手数料のどちらが高いかによります。
本記事では、実際に手数料がどのくらいかかるのか、その手数料を支払ってもiDeCoを利用した方が良いのか、について説明します。
最初に、おことわりです。
- 手数料は金融機関によって異なります。本記事では私がiDeCo口座を開設している、SBI証券を例に説明しています。
- 本記事は、所得控除額と手数料で比較しています。そのため後述しますが、例えば専業主婦の方は自動的に手数料負け、ということになります。
基本的に、手数料をふまえてもiDeCoを利用した方がお得です!
手数料との比較対象
iDeCoのメリットは、以下の3つです。
- 拠出した掛金全額が所得控除
- 運用益が非課税
- 退職所得控除、または公的年金等控除
上記3つは色々なところで説明されていますが、今回は手数料と比べてお得なのかどうか、という内容ですので、所得控除のみを対象とします。理由は以下に簡単に説明します。
拠出した掛金全額が所得控除
所得控除は、手数料との関係で大きく影響があります。
仮に、所得控除額が手数料と比べてお得でない場合、NISAで運用した方がお得だからです。
手数料が高いかどうかは、所得控除が手数料よりもお得かどうか、で決まるといっても良いでしょう。
運用益が非課税
運用益が非課税なのは大きいメリットですが、こちらはNISAも同様です。
また、NISA自体は、管理に手数料はかかりません。そのため、今回の議論からは外します。
退職所得控除、または公的年金等控除
iDeCoの特徴として、拠出時・運用時は非課税で、引き出すときに税金がかかるのが特徴です。こちらの控除に関する損得は、本業の退職金との兼ね合いもあるので、別途考える必要があります。
また、NISAで運用した場合は引き出す際に税金がかかりません。そのため、今回の議論からは外します。
手数料の種類
iDeCoの手数料は、以下の4つがあります。
- 加入時手数料
- 移管手数料
- 口座管理手数料(月額手数料)
- 受取時手数料
以下、それぞれ見ていきます。
加入時手数料
iDeCoへ新規加入する際にかかる手数料です。
開設する金融機関に関係なく、2,829円支払います。
移管手数料
iDeCoを運用する際に利用する金融機関を、変更する場合にかかる手数料です。
移管元・移管先の金融機関に関係なく、4,400円支払います。
もっとも、こちらの手数料は通常支払うことはないと思います。
口座管理手数料(月額手数料)
iDeCoを利用している方が、毎月支払うことになる手数料です。
詳細は後述しますが、基本的に毎月171円かかります。
受取時手数料
60歳以降、iDeCoで積み立てたお金を受け取る場合にかかる手数料です。
利用する金融機関に関わらず、振込1回で440円かかります。
iDeCoは、お金を受け取る場合に以下の2つから選択します。
・一括受取
・年金受取
一括受取の場合は、1回だけ440円かかりますが、年金受取の場合は毎回かかります。
今回、所得控除額と手数料の比較をしますので、本手数料はないものとします。
(一括の場合は1回きりですし)
口座管理手数料の詳細
口座管理手数料は、毎月かかる手数料のため資産運用に影響してきます。
以下の表をもとに、詳細を見ていきたいと思います。

今回は、加入者(掛金拠出者)について説明します。
運用指図者は、拠出期間は終わっているものの、年金受取を選択した等の理由でiDeCoでの運用を続けている方のことですが、加入者(掛金拠出者)で拠出しない場合と同様であるため、割愛します。
掛金を拠出した場合の手数料
掛金を拠出した場合の手数料は、171円+運営管理機関への手数料です。
運営管理機関への手数料は、金融機関によります。SBI証券の場合は無料ですが、金融機関によっては有料になります。
iDeCoは、開設する金融機関に制限はありませんので、ネット証券等、無料の金融機関を選びましょう。
掛金を拠出しない場合の手数料
掛金を拠出しない場合の手数料は、66円+運営管理機関への手数料です。国民年金基金連合会へ支払う105円分がなくなります。運営管理機関への手数料は、掛金を拠出する場合を同様で、金融機関によります。
掛金の拠出は月1回必須ではなく、回数を減らすことも可能です。
それでは、ここまで見てきた手数料が高いのか?について、以降で見ていきます。
手数料と所得控除額を比較するうえでの前提
手数料と所得控除額を比較するうえで、以下の前提をおきます。
- 拠出額は、毎月5,000円
- iDeCo以外の控除は考えない
以下、それぞれ見ていきます。
拠出額は、毎月5,000円
拠出できる額は、職業等によって変わりますが、最低拠出額は5,000円で一定です。
拠出額が多ければ多いほど、所得控除額も多くなります。また、金額に関わらず手数料は一定ですので、拠出額が低い方が手数料の割合は高くなります。
また、前述のとおり毎月拠出する方が、手数料は高くなります。
本記事では、毎月5,000円(年間60,000円)拠出で考えます。
iDeCo以外の控除は考えない
所得控除は、iDeCo以外にも多くの控除があります。配偶者控除や保険料等控除など、それらの加算によって所得税額も変わってきますが、前提を置きづらいので割愛します(当然ですが、基礎控除は加味します)。
本記事では、iDeCo以外の所得控除は考えないものとします。
手数料と所得控除額の比較結果
比較結果です。
結論としては、基本的に所得控除額の勝ちです。
手数料の合計
掛金を毎月拠出するため、手数料は毎月171円かかります。
年間では、171円×12ヶ月=2,052円です。
余談ですが、年間の拠出額は60,000円ですので、管理コストは約3.4%ということになります。
もし、投資信託の信託報酬が3.4%だったら、ボッタクリと言われますし、この管理コストを挙げて、そのように主張されている記事もありました。個人的には、メリットを差し置きすぎな意見だと思いますが、本記事では割愛します。
所得控除額
年収に分けて、一覧にしてみました。
| 年収 | 所得税額 (控除前) |
所得税額 (控除後) |
差額 |
| 200万円 | 23,400円 | 20,400円 | +3,000円 |
| 300万円 | 59,200円 | 56,100円 | +3,100円 |
| 400万円 | 96,900円 | 93,900円 | +3,000円 |
| 500万円 | 176,100円 | 169,900円 | +6,200円 |
| 600万円 | 278,200円 | 265,900円 | +12,300円 |
| 700万円 | 449,700円 | 437,400円 | +12,300円 |
| 800万円 | 633,500円 | 621,200円 | +12,300円 |
800万円より上の年収は、計算するまでもないですし、その方が月5,000円しか拠出できない、ということもないでしょう。
いずれの場合も、所得控除額が手数料を上回っています。
この結果から見ると、手数料を支払ってでもiDeCoを利用した方がお得、ということになりますね。
所得控除の恩恵がない方について
冒頭でも記載しましたが、所得税額が少ない方や、専業主婦のように所得がない方は所得控除の恩恵が受けられないため、手数料の観点から見るとiDeCoの利用は損、ということになります。
該当する方は、まずはNISAで限度額まで資産運用して、さらに非課税枠を使いたい場合にiDeCoを利用することなると思います。
個人的には、運用益の20%(今後増える可能性あり)を税金で引かれないことは大きなメリットですので、iDeCoも利用した方が良いと考えます。
おわりに
今回は、iDeCoの手数料は高いのか?について、所得控除額と比較する記事でした。
【2022年12月29日追記】
先日、源泉徴収票を会社から受け取って、自身も所得控除の恩恵を感じているところです。
iDeCoの運用成績や、どのくらい節税になったかについては、別記事で書きたいと思います。